ドゥービー・ブラザーズで好きなメンバーは俄然パトリック・シモンズ。
パトリック・シモンズ(Patrick Simmons) ことパットはドゥービーズのデビュー以来、
しかし、ドゥービー・ブラザーズと言えば、トム・
70年代前半ドゥービーズの豪快なロックが好きな人はトム・
70年代後半ドゥービーズのAORなサウンドが好きな人はマイケ
時期によって2人の音楽性が顕著に反映されているからだ。
このように、
またこの2人はボーカルも特徴的だ。
トミーは荒々しいロックサウンドに合う、

一方、マイクはスモーキーで深みのあるソウルフルなボーカル。
2人ともインパクトのある濃ゆい顔をしているが、
パットはといえば、クールでさわやかな声の持ち主だ。
顔も端正で容姿もスマートなナイス・ガイだ。
イケメンで声も良いパットだが、
…って結局顔じゃん!、と言われそうなので、
以下、特に好きなパットの10曲です。(リリース順)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
①South City Midnight Lady(『Captain and Me』収録)
フォークやカントリー・ミュージックからひときわ影響を受けたパットならではの曲。
歌詞はパットの故郷であるカリフォルニア州南部のサン・ノゼ(=サウス・シティー)の女性たちを讃えたもの。
カントリー・テイストを際立たせるペダル・スティール・ギターを演奏するのは、
当時スティーリー・ダンに在籍していたジェフ・“スカンク”バクスター。
ミドル・テンポの爽やかな曲調で、
カントリーを基調としているが、いなたさはなく、
タイトルの表す通り、
トミーのブルースに根ざした荒々しいロックサウンドと好対照を成す。
②Black Wlter(『ドゥービー天国』収録)
パットと言えばこの曲を挙げる人が多いのではないだろうか。
言わずと知れたドゥービーズ初のヒットナンバー。
歌詞はミシシッピへの憧憬にあふれ、旅情掻き立てられるものだ。
この歌詞の通り、ホンキー・トンク調な曲だけあって、
フィドルが効果的に演奏される。
途中で
このコーラスを発案したのはプロデューサーのテッド・
かつて彼自身が在籍していたハーパース・
同時期に活躍したウエスト・コーストのバンドでコーラス・
こちらのライブバージョンのジェフ・バクスターによるペダル・
曲の幽玄さを際立出せる。
③Neal's Fandango(『スタンピート』収録)
スピード感溢れるロック。
ダブル・ドラムとトリプル・ギターが力強く疾走する。
まさに“
リトル・フィートのメンバーであるビル・ペインの鍵盤が入り、
ここでも素晴らしいコーラスが聴ける。
1分45秒辺りからダイナミックなスケープが広がっていくように、
これぞバーバンク・サウンド。
こうしたサウンドもプロデューサーのテッド・
メンバーとエンジニアのドン・ランディと共に裏ジャケに映るテッド(下段右から2番目)
因みにニールとはビート詩人のニール・キャサディのことで、同アルバム収録の「I Cheat The Hangman」にも見られる、ストーリー性ある歌詞となっている。
こうした捻りの効いたパットの歌詞は、音楽一筋な歌詞が多いトミーや恋愛ソング中心のマイクとは一線を
こちらのライブの演奏もとてつもなくエキサイティング。
間奏のギター・ソロで暴れまくるジェフ・バクスターが最高。
④Slat Key Soquel Rag(『スタンピート』収録)
パットと言えばアコギのフィンガーピッキング。
ここではお得意のラグ・タイム奏法を。
歌なしだが、ギター・インストとして充分楽しめる曲。
パットはAOR路線に突入後も、「Larry The Logger Two-Step」や「Steamer Lane Breakdown」といったカントリー調インストナンバーを1アルバムにつき1曲取り入れ続けた。
⑤8th Avenue Shuffle(『ドゥービー・ストリート』収録)
舞台はニューヨーク。
かつて歌われた南部への憧憬に対し、本作では都会の喧騒が陽気に歌われる。
トミーの体調不良によるバンドの脱退により、
スティーリー・ダンからジェフ・バクスターとマイケル・
パットの楽曲も音楽的に一層幅広いものになっていった。
本作はメンフィス・ホーンのソウル・フルな演奏や変速リズムが取り入れられ、
サウンドにおける目覚ましい変化が楽しめる。
また、パットとスカンクの異なる個性を持ったギター・プレイの対比も面白い。
ラテン風のギターリフを基調とし、
カリフォルニアの片田舎から、大都会ニューヨークへと、
ドゥービーズは都会的なサウンドに移る。
⑥Rio(『ドゥービー・ストリート』収録)
「8th Avenue Shuffle」と同じくラテン調の曲ではあるが、洗練度が大幅に増す。
サンバ風のパーカッションとジャジーなエレピによるイントロにベ
リオのカーニバルよろしく、解放感に満ち溢れる。
万華鏡のようなコーラス・ワークは楽曲に煌めきを与える。
「ねえ、乗ってかない?」
というワンフレーズだけ登場するマリア・マルダーが何とも粋な演出だ。
⑦Echoes Of Love(『運命の掟』収録)
パットの曲にもマイケル・
パット作のこの曲も、
イントロも曲全体のアレンジもマイクのシンセが中心である。
キャッチーなシンセのリフがいかにもマイクらしい。
パットによるメロウなメロディーと爽やかなボーカルはマイクのサ
シングルとしても発売された。
⑧Livin' On The Fault Line(『運命の掟』収録)
より複雑化するリズム。
より深遠化するグルーヴ。
同アルバム収録の 「China Groove」に通じるインプロビゼーション・ナンバー。
ファンキーでジャズ色の強いプログレッシブな楽曲であり、パット、そしてドゥービーズの新境地と言える。
後半にかけて曲が盛り上がっていく様は、
ビブラフォンが効果的。
こうした曲もトミーやマイクには無いもので、
カントリーやメロウ路線とは別のパットの持ち味が発揮されている
アルバムの表題曲。
⑨Sweet Feelin'(『ミニット・バイ・ミニット』収録)
アコーステック・ギターの音色が優しく響く、
ワーナーのレーベルメイトであるニコレット・
呼応するようなコーラス・ワークも甘美。
プロデューサーのテッド・テンプルマンも共作し、
彼の叩き出すサウンドは曲のソフトな印象を際立たせる。
まさにSweet Feelin'な曲。
⑩If You Want A Little Love(『メロウ・アーケード』収録)
最後はパットの唯一のソロアルバムから。
1982年にドゥービーズを一旦解散させたパットは翌年ソロ作をリリースする。
トミーからマイクまでお馴染みのメンツも参加。
楽曲はカントリー調のものやポップ・ソウル風ナンバー等、ドゥービーズ・サウンドを彷彿とさせるものに交って、
ハード・ロックやディスコ風といったアレンジやヒューイ・ルイスのカバー等、ドゥービーズ時代のパットらしからぬ楽曲も見られる。
本作「If You Want A Little Love」はディスコAORな楽曲。
咲き乱れるような早口コーラスが何ともユニーク。
タワー・オブ・パワーによるホーンが彩りを添える。
タワー・オブ・パワーによるホーンが彩りを添える。
パットの新たな一面が垣間見える楽曲となっている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上パットの魅力を掘り下げてみました。
メンバーチェンジによってバンドの音楽性が大きく変化するに伴い
つまり、強引に言い方をしますと、パットの歴史=
パトリック・シモンズこそドゥービーズの要だ。
と、冒頭で豪語しましたが、

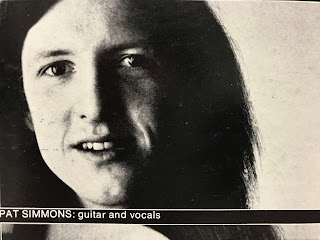
0 件のコメント:
コメントを投稿